標茶の梯子乗りの歴史は古く、大正時代に始まりました。しかし時代の流れには逆らえず昭和36年の出初式以降中止とされていました。しかし古き良き時代の伝統を保存していこうと平成4年標茶消防百年を記念し再興されました。梯子乗りとあわせまとい振りも行われており出初式、祝いの行事には欠かせないものとなりました。

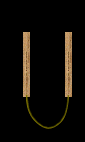
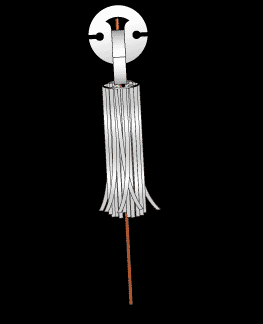


まとい組組員(消防団員18名 消防職員11名 計29名)
組頭 鈴木勝巳 小頭 蛯名嘉章 畠山雅之 事務局長 飯田徹 事務局 越善忍
組員
山崎孝一 田中敏文 山林幹雄 小野寺一史 小山内政二 村上徳幸 野田雄一
小渡幸次 遠藤優一 木下徹 武山幸男倉内秀和 佐藤紀寿 荒井秀基 渡辺大治
前島仁 越善忍 鈴木利弘 加藤悦久 田中稔 高橋行 高田貢 小野寺将人
佐藤直幸 矢島幸宏
纏(まとい)振りの演技種類とその説明
●三三九度
この振り方はおめでたい席又は祝いの行事があるときにふられた型であるといわれています。
右手を三三九度の時の盃にたとえている。
●木遣奴振り(きやりやっこふり)
この振り方は出初式その他の催し物で町の中を纏振りをしながら行進するときに木遣を歌いながら
火消し全員が纏振りと一緒に練り歩く時の型と言われている。
●一文字流し
木遣奴振りと同様
●神田奴振り(かんだやっこふり)
この型は、いろは四十八組の一つ神田佐久間町島1丁目から6丁目湯島天神一帯を守る町火消し
「か組」の流れを組む纏振りの型と伝え聞いています。
平成19年には鵡川消防纏保存会より纏振りの指導を受ける

梯子(はしご)乗り
まとい組は纏振りの他梯子乗りも実施しています。
演技種目
上芸(梯子の上で行う技)
達磨遠見(だるまとうみ)、一本遠見、鯱(しゃちほこ)、唐傘(からかさ)
爪掛け八艘(つめかけはっそう)、一本八艘(いっぽんはっそう)、腹亀、背亀、
肝潰し、枕邯鄲(まくらかんたん)、一本邯鄲(いっぽんかんたん)
中芸(梯子の中途で行う技)
腕溜め、膝掛け、膝留、大の字、
膝 留
腕溜め
一本邯鄲
肝潰し
背 亀
二本腹亀
腹 亀
爪掛け八艘
達磨遠見








